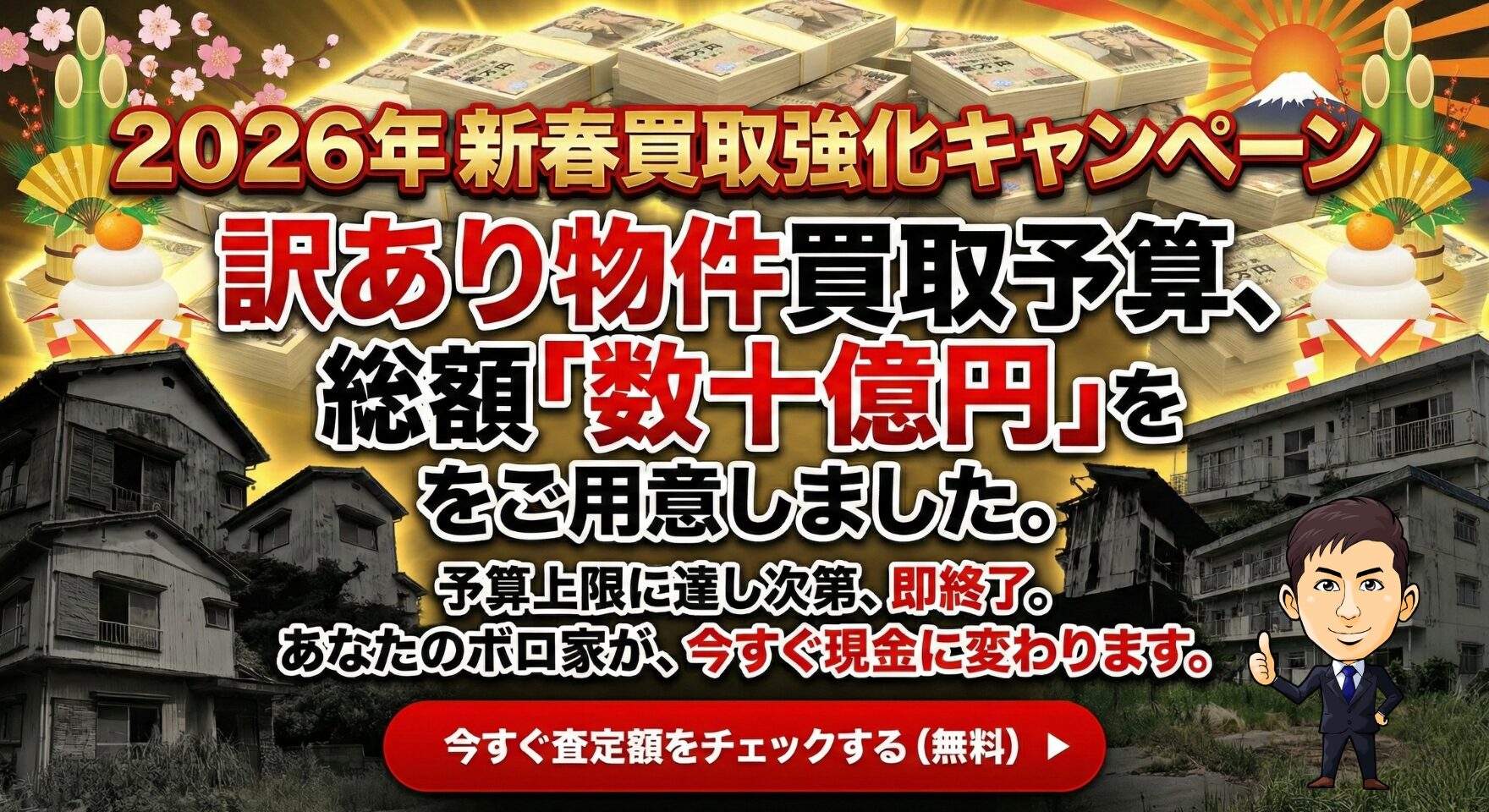賃貸中の物件を入居者へそのまま売却する際のポイント
賃貸中の物件を、そのまま入居者に売却する手法が注目されています。
空室にしてから売る場合と比べて、時間やコストを大きく抑えられるだけでなく、入居者にとっても住宅ローンを利用しやすく、引越しの手間を省けるため、結果的に売却価格や交渉が有利に進む可能性が高いからです。
今回は、この方法がどのようにメリットをもたらすのか、売買の流れや注意点をわかりやすく解説します。
賃貸物件を入居者へ売却するとは
賃貸物件を入居者へ売却するという方法は、これまであまり一般的に知られていませんでしたが、近年ではより効率的に物件を手放したいオーナー様の間で注目を集めています。通常、不動産を売却する際には空室にしてから買い手を探すケースが多いかもしれません。
しかし、賃貸契約中の物件をそのまま入居者へ売却することで、賃貸収益を維持しつつスムーズに話を進められる可能性が高まるのです。
たとえば、いざ空室にしてしまうと、新しい入居者が見つかるまで収益が途絶えてしまったり、リフォームやクリーニング費用をかけなくてはならない場合があります。
そうしたコスト面のリスクが抑えられるうえ、入居者にとっては住み慣れた場所を買うことができるので、安心感が大きいのです。
さらに、貸主・借主が直接交渉を行うことで、お互いの事情を理解しながら進めることができるのもポイントです。
賃貸借契約が継続している段階で売買を行う場合には、敷金の処理や契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の範囲など注意点もありますが、正しい知識を身につければリスクを最小限に抑えられます。最近ではノンリコースローンの活用を検討する方や、金融検査マニュアルを意識しながら資金計画を立てるオーナーも増えており、時代の変化に合わせた売却方法として注目度が高いといえるでしょう。
賃貸物件を入居者へ売却するとは、ただ契約を結ぶだけでなく、入居者にとってもオーナーにとっても、従来の手放し方よりもメリットの多い新しい選択肢なのです。
賃貸中の物件を入居者に売却するケースが増えている背景
近年、賃貸中の物件を入居者に売却するケースが増えているのは、社会的環境や経済状況の変化が大きく影響しています。
まず一つ目の理由として、低金利の時代が長く続いているため、入居者が住宅ローンを組みやすくなっていることが挙げられます。
たとえば、以前は「家賃を支払うよりも購入したほうが安い」という発想になかなか辿り着けなかった方も、金利水準が下がることで月々の支払額が家賃と大差ない、もしくは安く抑えられると気づくようになりました。また、仕事や生活スタイルが多様化したことにより、今住んでいる場所を購入して腰を据えて暮らしたいと考える人が増えています。
さらに、売主(オーナー)側にとっては、空き家リスクや空室期間による家賃収入の減少を避けられるため、入居者への売却を望むケースが急増しています。
こうした背景から、不動産業界では賃貸物件を入居者に売却するためのノウハウが蓄積され、従来よりもスムーズな取引が実現しやすくなってきました。
まさに、時代の流れが「賃貸中の物件を入居者に売る」という選択肢を後押ししていると言えるでしょう。
「オーナーチェンジ物件」との違い

「オーナーチェンジ物件」という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。
オーナーチェンジ物件とは、すでに入居者がいる状態の物件を第三者に売却し、買主がそのまま賃貸借契約を承継する形態を指します。たとえば、収益物件としての投資目的で購入されるケースが一般的です。
これに対して、賃貸物件を入居者へ売却する場合は、入居者自身が買主となるため、契約の形態や目的が根本的に異なります。
オーナーチェンジ物件の場合は、買主が家賃収入を得ることを狙いとしていることが多いのに対し、入居者へ直接売却する場合は自己居住を目的とした購入になるため、住宅ローン利用がしやすいメリットが生まれるのです。
また、従来のオーナーチェンジ物件では、買主と既存の入居者の間に直接的な利害関係はあまり生じませんが、入居者へ売却する場合は、もともと生活者として物件の状況を熟知しているので、買主にとってリスクが少ない面が特徴といえます。
さらに、オーナーからすれば、レントロールを見せる必要がないケースも多く、手続きや契約条件がシンプルになる場合が多いです。こうした違いを理解しておくことで、自分がどのような目的で売却したいのか、入居者がどんな条件で購入を考えているのかをしっかり確認しながら取引を進めることができます。
賃貸物件を入居者へ売却するメリット
賃貸物件を入居者へ売却するメリットは、売主・買主の両者にとって多岐にわたります。まず、売主側には空室リスクやリフォーム費用を軽減できるという点が大きいでしょう。
通常、物件を売却する際に空室にしてしまうと、その間の家賃収入が途絶えてしまうため、オーナーにとっては大きな痛手となります。また、経年劣化が進んだ部分を修繕してから売りに出す必要がある場合には、思った以上に費用がかかることも珍しくありません。
一方で、入居者側にとっては、引越しの手間を省きつつ住宅ローンを利用することで、家賃と同程度、もしくはそれ以下の支払いでマイホームを手にできる可能性があります。
このように、双方がウィンウィンの関係を築けるのが、賃貸物件を入居者へ売却する際の最大の魅力といえるのです。
さらに、不動産鑑定評価基準や登記簿謄本の内容を詳しく確認するまでもなく、現住者が物件の状態をよく知っているため、後々のトラブルを避けやすいのもメリットといえるでしょう。
売主(貸主)のメリット:高値売却・スムーズな契約
売主(貸主)にとって賃貸物件を入居者へ売却する最大の魅力は、高値での売却が期待できることと、スムーズな契約手続きです。通常、空室となった物件は買い手にとってリフォーム費用や内見のコストなどを考慮した値引き交渉が行われる場合が多く、想定より低い価格で売らざるを得ないことがしばしばあります。
しかし、入居者が直接購入する場合、引越し費用や新たな住環境を探す手間が不要になることを考慮して、多少高い金額でも納得してもらえることがあるのです。その結果として、売主が想定していた価格に近い売却額が得られる可能性が高まります。
さらに、賃貸借契約から売買契約に移行する過程は、入居者との信頼関係を活かすことで、余計なトラブルや時間をかけずに進めることができます。
契約手続きに関しては、不動産会社が間に入ってアドバイスをしてくれる場合も多く、敷金の精算や契約不適合責任の免責条項などについてもスピーディーに話し合えるでしょう。
つまり、売主にとっては高値売却と手続きの簡略化が同時に得られる魅力的な方法なのです。
買主(借主)のメリット:引越し不要・住宅ローン減税など
買主(借主)にとってのメリットは、とても身近で実感しやすいものばかりです。
まず挙げられるのが、引越しの手間と費用を省けることです。通常、新居を購入する場合には、内見から契約、引越しまでさまざまな段取りが必要になり、それには多額の費用と時間がかかります。
しかし、今住んでいる物件をそのまま買うのであれば、もちろん住所も変わらず、近所付き合いも維持できるため、精神的な負担も少なくなるでしょう。また、住宅ローンを利用することによって、家賃よりも低い月々の支払いを実現できる場合や、住宅ローン減税を活用して税金の優遇を受けられる可能性が高まります。
たとえば、年末残高に応じた控除を受けられる制度が適用されれば、実質的な負担額を大幅に抑えることができます。さらに、実際に暮らしてきた物件なので、周辺環境や設備の状態を熟知しているため、想定外のトラブルに見舞われるリスクが少ないのも大きなメリットです。
こうした安心材料があるからこそ、借主が躊躇なく購入を検討しやすいのです。
売却に向けた準備と流れ

賃貸物件を入居者へ売却しようと考えるときには、いくつかのステップを踏む必要があります。まずは、物件の査定や入居者への打診、そして価格交渉や契約締結までの一連の流れをしっかりと把握することが大切です。
たとえば、相場よりも大幅に高い価格を提示してしまうと、どんなに住み慣れた物件でも入居者が購入を諦めてしまう可能性がありますし、逆に低すぎるとオーナー側にとって不利な取引となってしまいます。
また、仲介手数料の上限額を含む費用面の計算や、必要書類(登記簿謄本や固定資産税通知書など)の整理も重要です。こうした準備を丁寧に行うことで、売却の話を進める際に余計な混乱を招かず、スピーディーに手続きを終えられるでしょう。さらに、入居者が住宅ローンを組む場合には、金融機関の審査スケジュールも考慮しなくてはなりません。
あらかじめ、どのタイミングでローンの事前審査や本審査を進めてもらうかを入居者と共有しておくことが、円滑な売却につながります。このように、準備段階での情報収集と計画立案が成功の鍵を握るのです。
物件の査定依頼と相場価格の把握
物件の査定依頼と相場価格の把握は、賃貸物件を入居者へ売却するうえでの最初のステップといえる大切な工程です。なぜなら、適正な価格を知っていないと、そもそも入居者との交渉が成り立たず、せっかくの好機を逃してしまうからです。
まずは信頼できる不動産会社や不動産鑑定士に査定を依頼し、物件の現在価値を客観的に算出してもらいましょう。その際、不動産鑑定評価基準に基づいた評価を行ってくれる会社を選ぶと、より正確な数字が得られやすいです。
査定結果を受け取ったら、インターネットで周辺エリアの成約事例や売り出し中の物件価格をチェックし、相場価格と照らし合わせてみると良いでしょう。
たとえば、「同じ沿線にある2LDKのマンションで築年数が近いものが、どれぐらいの価格帯で売れているのか」などの情報を参考にします。
こうして得られた相場観を踏まえ、入居者に提示する売却希望額を検討することが大切です。あまりにも相場からかけ離れた金額を設定すると入居者が興味を失ってしまうため、慎重に見極める必要があります。
入居者への打診と意思確認
物件の相場観と査定額がはっきりしたら、次に行うべきは入居者への打診です。
賃貸契約中の物件を売却する際には、入居者が購入に積極的かどうかを見極めることが不可欠です。まずは、丁寧な言葉遣いで「物件を売却する可能性があるが、購入の意向はあるか」と尋ねましょう。
このとき、相手の経済状況や将来設計に配慮することが大事です。たとえば、「家賃を払う代わりに、同じような額でローンを組めば資産になる」という点を分かりやすく伝えると、購入に前向きになってもらえる場合があります。
また、入居者によってはローン審査に不安を感じていることも多いので、金融機関や不動産会社と連携して事前相談のサポートを行うとよいでしょう。さらに、打診の際には売却希望額と大まかなスケジュールを提示してあげることで、入居者の検討がスムーズに進みます。
もしも入居者が購入を拒否したり、難色を示している場合には、価格の再検討や購入サポート方法の見直しが必要になるかもしれません。
価格交渉と売買契約の締結
入居者が購入に興味を持ってくれたら、次は具体的な価格交渉に入ります。
ここではお互いの妥協点や希望条件をすり合わせる作業が重要です。たとえば、「家賃の8割程度の金額を住宅ローン返済に充てられるのであれば購入したい」と入居者が希望する場合や、「何か設備交換が必要な部分があれば修理費を負担してほしい」といった要望が挙がるかもしれません。
そうした場合、売主側は査定額や相場価格、物件状態などをもとに、どこまで譲歩できるかを検討します。もし双方が納得できる価格帯に落とし込めたら、不動産会社などを通じて正式な売買契約を結びます。
契約書には、「賃貸借契約の消滅タイミング」や「敷金の扱い」「契約不適合責任の免責範囲」など、通常の売買契約以上に注意を払うべき項目が多く含まれますから、専門家のアドバイスを受けながら慎重に取り決めることが大切です。
最終的にお互いが納得できた時点で、手付金の受領、決済日や物件の引き渡し時期を確定し、売買契約の締結となります。
売買交渉の窓口について

賃貸物件を入居者へ売却する際には、どのように交渉を進めるかが非常に重要です。大きく分けて「貸主と借主が直接やり取りする」「賃貸管理会社を間に入れる」「売買仲介会社を利用する」という三つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合った選択を見極めることが大切です。たとえば、普段から入居者とコミュニケーションが取れている場合は直接交渉がスムーズに進むかもしれません。
しかし、専門家しか知り得ない法的ポイントや宅地建物取引業法に基づく説明義務などをカバーできない場合もあるため、慎重さが求められます。逆に、売買仲介会社を利用すれば法的リスクや事務作業を大幅に軽減できる一方で、仲介手数料が発生することになります。
賃貸管理会社を窓口とするケースでは、既に信頼関係がある一方で、管理会社が売買の専門知識を十分に持っていない可能性もあるのです。
こうした選択肢を整理して、自分に合った方法でスムーズな売却を目指しましょう。
貸主と借主が直接やり取りする場合の注意点
貸主と借主が直接やり取りをする場合、コミュニケーションがダイレクトに行われるため、話が早いというメリットがあります。お互いの時間を調整しやすく、希望条件もその場で交わせるので、ストレスなく売買交渉が進むかもしれません。
しかし、その反面、専門知識を持った第三者が介在しないことで、契約に関するリスクを見落とす可能性がある点に注意しましょう。たとえば、敷金の精算方法や契約不適合責任の免責範囲は、賃貸借契約と売買契約を行き来する内容であるため、思わぬトラブルに発展しやすい分野です。
さらに、話し合いがうまくいかない場合には、入居者がこれまで通り住み続けることになるため、人間関係がぎくしゃくしてしまうリスクも考えられます。こうした状況を防ぐためには、あらかじめ法律や契約の仕組みをしっかり把握しておき、必要に応じて行政書士や司法書士、不動産会社にアドバイスを求めることが大切です。
賃貸管理会社を通す場合のメリット・デメリット
賃貸管理会社を通すケースでは、日頃から貸主と借主の間に入って物件管理を行っている会社が窓口となるため、信頼感が得やすいというメリットがあります。
たとえば、入居者の生活スタイルや支払い状況を把握しているため、売買に関する相談もスムーズにスタートできるでしょう。さらに、管理会社がオーナーの意向をしっかり理解していることが多く、必要な情報をまとめてくれる可能性があります。
一方で、賃貸管理会社が売買契約の専門知識を十分に持っているとは限りません。宅地建物取引業の免許を持っていたとしても、日常的に売買仲介を行っていない会社の場合、契約不適合責任の詳細や住宅ローンを利用する際の注意点などを的確にサポートできないことがあります。
また、管理会社に売買仲介の報酬が入らない場合、あまり前向きに動いてもらえないケースもあるかもしれません。こうしたデメリットをカバーするために、必要に応じて売買仲介を専門とする会社の協力を仰ぐことも視野に入れておくと安心です。
売買仲介会社を利用する場合のメリット
売買仲介会社を利用する場合、最も大きなメリットは売買契約に精通したプロのサポートを受けられることです。
たとえば、契約不適合責任の範囲や抵当権抹消の手続きなど、専門家しか知り得ない知識やノウハウをフル活用して、スムーズな取引を実現してくれます。
また、契約書類の作成から金融機関とのやり取りまで、煩雑な事務作業を仲介会社が担うため、貸主と借主双方の負担が大きく軽減されるのです。
さらに、公正な立場から貸主・借主の間を取り持ってくれるため、価格交渉や引き渡し日の調整といったデリケートな話題もスピーディーにまとめやすくなります。
もちろん、仲介手数料はかかりますが、手厚いサポートを受けることでトラブルや時間のロスを防ぎ、結果的に満足度の高い売買を実現できる可能性が高いでしょう。特に、賃貸借契約と売買契約が絡み合う複雑な場面では、売買仲介会社の存在が大きな安心材料となります。
賃貸借契約と売買契約の関係

賃貸物件を入居者へ売却する場合、賃貸借契約と売買契約がどのように絡むのかを正しく理解することが、円滑な手続きを進めるうえで重要です。
なぜなら、賃貸借契約には敷金や更新料などの取り扱いがあり、それらが売買契約によってどのように処理されるのかを明確化しないと、後になってトラブルに発展する可能性があるからです。
また、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の範囲や特約事項がどのように設定されるかによって、入居者が購入後に建物の不具合を発見した場合の責任分担が変わってくることもあります。
さらに、すでに賃貸借契約で保証人を立てているケースでは、新たな売買契約での保証内容との整合性を確認する必要も出てくるかもしれません。
賃貸借契約の消滅タイミングと敷金の扱い
賃貸借契約の消滅タイミングは、売買契約締結時ではなく、物件の引き渡し(決済)と同時に終了することが一般的です。つまり、所有権移転の瞬間をもって賃貸借契約も同時に消滅し、それ以降は買主である入居者の持ち物という扱いになります。
このとき、敷金の扱いがポイントになります。通常のオーナーチェンジ物件であれば、買主が賃貸人の地位を引き継ぐため、敷金も承継されますが、入居者自身が買主になる場合は少し状況が異なります。
賃貸借契約が終了する以上、本来は敷金を入居者に返還する必要があり、それと同時に買主としての売買代金を支払うわけです。実務上は、敷金分を売買代金と相殺する形をとることも多いため、契約書にその点を明記することでスムーズな精算が行われます。
たとえば、「敷金○○円は売買代金の一部として充当する」といった特約を設けることで混乱を避けられるでしょう。こうした細かな取り決めを怠ると、後になって「敷金を返すはずだったのに返金されていない」というトラブルが生じる場合がありますから、必ず契約書に明記するのがベストです。
付帯設備表の不交付と物件状況報告書
賃貸中の物件を入居者に売却する際には、通常の売買と異なり、付帯設備表を交付しないケースが多いとされています。なぜなら、入居者はすでに物件内部を十分に知っているため、改めて「どんな設備があるのか」を確認する必要性が低いからです。
しかし、だからといって設備の不具合があった場合の責任問題がなくなるわけではありません。そのため、物件状況報告書については売主が作成しておくことが望ましいとされています。
特に、売主しか知り得ない不具合や修繕歴がある場合には、後々のトラブルを避けるためにも正直に開示したほうが双方にとってメリットが大きいでしょう。
たとえば、以前に雨漏りがあったものの修理済みである場合や、設備交換を行った際の記録などは、買主にとって重要な情報です。報告書を作成するときには、不動産会社の書式を利用したり、弁護士や行政書士にチェックしてもらうと安心です。
こうした情報開示の姿勢が、売主と買主の信頼関係を強化し、後々の紛争を避ける大きなカギとなるのです。
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の免責範囲
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)は、売買契約時に想定していた物件の状態と実際の状態が異なる場合に、売主が負う責任を指します。賃貸物件を入居者に売却する場合、買主はすでに住んでいるため、物件の状況を熟知しているケースが多いですが、それでも隠れた欠陥が発見される可能性はゼロではありません。
たとえば、配管の奥深くにある水漏れや、建物構造部分の重大なひび割れなどは、日常的には気づきにくいかもしれません。そうした点で、売主と買主がどこまで責任を負うのか、契約書に明記することが重要です。
一般的には、エアコンなどの設備については「現状有姿」で引き渡すことが多く、建物の主要構造部分については一定期間の補修義務を負うケースが多いです。
ただし、売主が宅地建物取引業者や法人で、買主が個人の場合は、消費者契約法の観点から過度な免責が無効となることもあるため、注意が必要です。実務では、それぞれの物件の状況に応じた特約を定めることでトラブルを予防します。
住宅ローン利用時のポイント

入居者が物件を購入する際、多くの場合は住宅ローンを利用します。実は、賃貸物件として住み続けるわけではなく、自分で所有することになるため、投資用ローンよりも金利の低い住宅ローンを組める可能性が高いのです。
ただし、審査の際には「現在の家賃とローン返済額の比較」や「物件の担保価値」などが重視されます。たとえば、借主が長年安定した家賃支払い実績を持っていれば、金融機関から信用を得やすいでしょう。
一方で、契約不適合責任の範囲や建物の老朽度によっては、担保評価が下がり融資額が抑えられるケースもあります。また、住宅ローン減税の適用条件を満たすかどうか、固定資産税の優遇措置が受けられるかといった税務面の確認も重要です。
こうした条件を把握することで、借主は無理のない返済計画を立てやすくなり、売主側もスムーズに決済できる日程を組むことができます。総じて、住宅ローン利用は双方にメリットをもたらす反面、事前のリサーチや金融機関とのやり取りがカギを握るポイントなのです。
入居者が住宅ローンを組む際の流れ
入居者が住宅ローンを組む際の流れは、基本的には通常の住宅購入と大きく変わりませんが、賃貸物件の売買という特殊な状況に合わせて若干の注意点があります。
まず、入居者は希望する金融機関や金利タイプ(固定金利、変動金利など)を選び、事前審査を受けます。ここで重要なのは、入居者が現在支払っている家賃や収入状況を正確に申告することです。
審査が通れば、本審査に移りますが、この段階で物件の担保評価も行われます。賃貸借契約から売買契約に移行するため、金融機関によっては追加書類を求められることがあります。
たとえば、現在の契約書や修繕履歴、管理費の支払い証明などです。その後、正式に承認が下りたら売買契約を結び、決済日にローンが実行される流れです。
ローン実行と同時に所有権移転登記を行い、賃貸借契約が消滅するため、敷金の精算や各種費用の支払いをスムーズに行えるよう準備しておきましょう。
金融機関の審査と事前相談
金融機関の審査では、入居者の返済能力と物件の担保価値が大きなポイントになります。
借主の勤務形態や年収、他の借入状況はもちろんのこと、購入しようとしている物件が一定の耐震基準を満たしているか、違法建築ではないかなどを細かくチェックされます。
とくに古い物件や特殊構造の建物の場合、担保評価が下がって希望額の融資が受けられないケースもあるため、事前に相談しておくとよいでしょう。
たとえば、「築古物件だけれど、大規模修繕を定期的に実施している」場合などは、管理状況の資料を提示することで評価が上がる可能性があります。また、住宅ローン減税を受ける場合は、登記面積や耐震基準適合証明書なども確認されるため、必要書類をそろえておくことが賢明です。
金融機関との事前相談を重ねることで、無理のない返済計画を立てられ、売買契約締結後に「融資が下りなかったので買えない」というトラブルを避けられます。
まとめ
賃貸物件を入居者へ売却することは、お互いに大きなメリットを得られる可能性を秘めています。
一方で、賃貸借契約の終了や敷金精算、契約不適合責任など、通常の売買以上にチェックポイントが多いのも事実です。しっかりとした知識と準備をもって臨むことで、スムーズで円満な取引を目指しましょう。
スムーズな交渉と円満な手続きのために
スムーズな交渉と円満な手続きのためには、まず賃貸借契約と売買契約のポイントを正しく把握することが欠かせません。具体的には、所有権移転と同時に賃貸借契約が終了するタイミングや、敷金の精算方法、付帯設備や契約不適合責任の範囲など、入居者と共通認識を持つべき項目は多岐にわたります。
また、価格交渉や住宅ローン利用のプロセスで意見の相違が出た場合は、無理に押し通すのではなく、ファイナンシャルプランナーや不動産会社に相談しながら第三者的な視点で解決策を探すとよいでしょう。