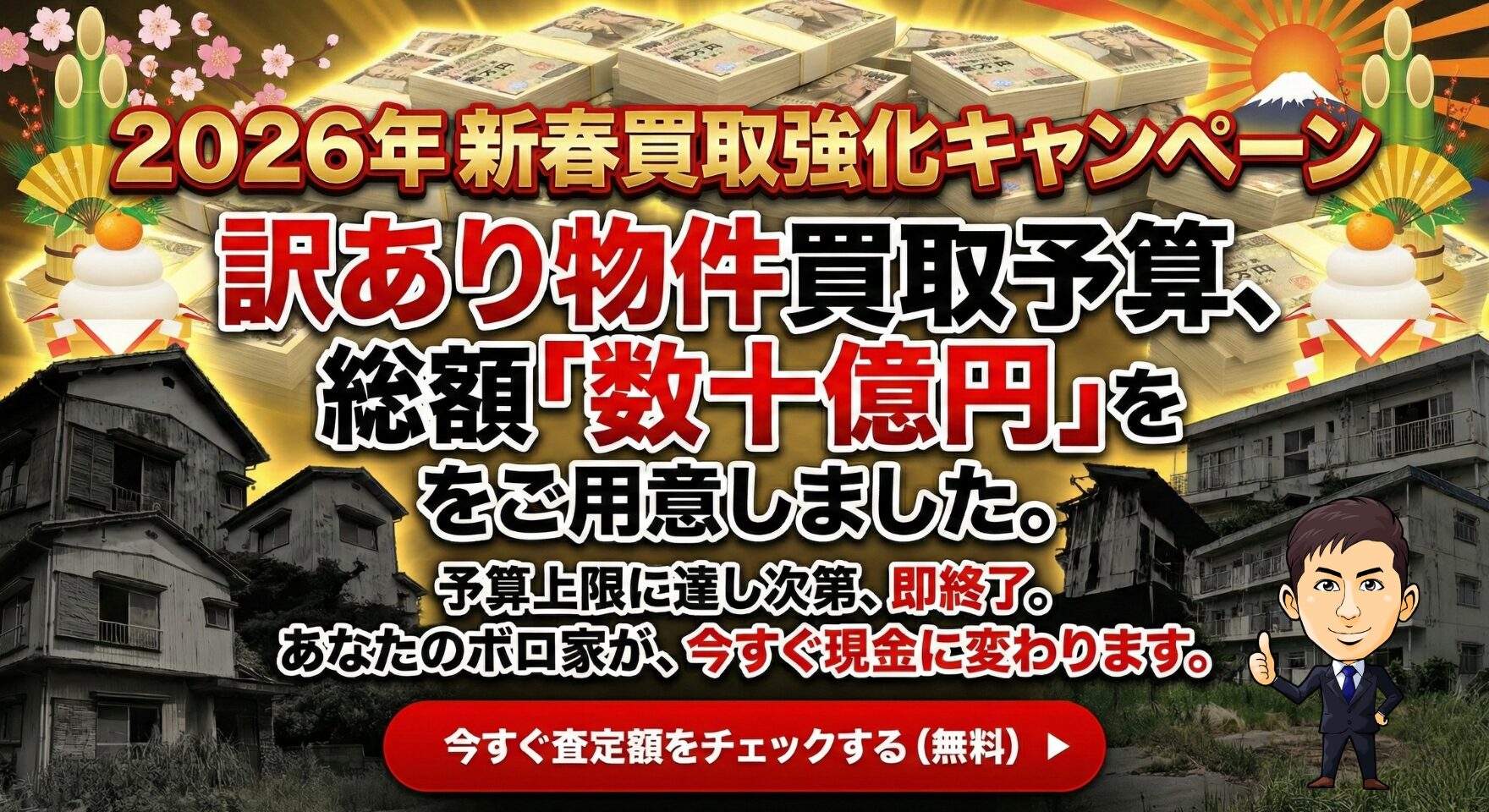相続放棄した空き家の解体費用や損害賠償のリスク
相続放棄した家でも、完全に責任がなくなるわけではありません。相続放棄後も、家を放置して倒壊の恐れなどがある場合は解体費用や損害賠償のリスクが残るためです。
たとえば、老朽化した空き家が崩れて隣家に被害を与えた場合、思わぬ賠償金が請求されることがあります。
相続放棄を考えるときは、解体費用や管理責任の仕組みを理解し、早めに対策することが大切です。
相続放棄した家と解体費用の問題
相続放棄を検討している方の中には、
- 「家が古くて解体しなければいけないけれど、高額な費用がかかってしまうのではないか」
- 「相続放棄をすれば家の管理や費用の負担から完全に解放されるのではないか」
といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、相続放棄をしても状況によっては解体費用や管理責任が生じることがあります。
さらに、空き家のまま放置してしまうと行政代執行が行われ、知らないうちに多額の費用を請求されるリスクも否定できません。
こうした問題を回避するためには、相続放棄の基本的な仕組みや法律で定められている義務について正しく理解することが重要です。
例えば、「保存義務」や「行政代執行」の手続きなど、少し専門的な単語が出てきますが、要点を押さえれば中学生でも理解できる内容です。本記事では、相続放棄と空き家の解体費用にまつわる疑問を、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
しっかりと知識を身につけておくことで、思わぬ負担やトラブルを防ぎ、安心して相続放棄や家の処分を進められるようになります。
相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金などを一切引き継がない手続きを指します。
通常、相続はプラスの財産だけでなくマイナスの負債も引き継ぐため、「家のローンがある」「維持管理に多大な費用がかかる」などの理由から、相続自体を放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、一度相続放棄をすると、原則としてその相続に関しては財産を受け取ることができなくなるため、手続きに迷うことも少なくありません。さらに、相続放棄をしても空き家などの不動産に関しては別の問題が発生するケースもあります。
例えば、すでに管理を始めていた家を手放そうとしても、「占有していた期間の保存義務」などが原因で思わぬ出費が生じる可能性もあるのです。
こういった状況を避けるためには、相続放棄の制度をしっかりと理解し、自分にとって最善の選択肢を考える必要があります。専門家が使う言葉では「法定単純承認」や「限定承認」などの概念もありますが、基本は「すべて放棄するか、引き継ぐか」の二択が大まかな流れです。
相続放棄の基本的な仕組み
相続放棄の基本的な仕組みを理解するためには、まず「相続開始の時点で何を受け取るか」という考え方を押さえることが大切です。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行い、正式に「すべての遺産を引き継がない」旨を認めてもらう手続きになります。
これにより、プラスの財産はもちろんマイナスの負債も継承しないことになりますが、手続きの期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と法律で定められています。
また、相続放棄をした後で財産を処分してしまうと、法律上は「相続を承認した」とみなされ、放棄が無効となることがあるので要注意です。下記のポイントもぜひ把握しておきましょう。
相続放棄が選択される主な理由
相続放棄を選ぶ理由は人によってさまざまですが、主に次のようなケースが多く見受けられます。
- 被相続人に大きな借金があった
- 家屋が老朽化し、解体費や修繕費が高額になる
- 不動産が遠方にあって管理が困難
たとえば、都会で生活している人が地方にある空き家を相続すると、管理のために定期的に足を運ばなければならず、時間や交通費などの負担がとても大きくなります。
また、家屋の状態が悪いとリフォームだけでも数百万円、解体となるとさらに費用がかさむため、とてもではないが負担しきれないと思われることも珍しくありません。こういったケースでは、「相続してもメリットが少ない」と判断し、相続放棄の手続きを選ぶ方がいらっしゃるのです。
さらに、被相続人が複数の債務を負っていた場合や、抵当権が設定されている不動産があった場合なども相続放棄を検討する主要な要因となります。
相続放棄は経済的リスクを回避するための有効な手段ですが、後ほど解説するように「保存義務」や「行政代執行」といった問題も絡んでくるため、慎重に判断することが求められます。
相続放棄と空き家にかかる解体費用
相続放棄を考える際に、特に気になるのが空き家の解体費用です。「相続放棄をすれば、家に関するすべての費用から解放されるのではないか」と思われる方も多いかもしれません。
しかし実際には、相続放棄をしたとしても、ケースによっては空き家の解体費用を請求されたり、管理責任を問われたりすることがあるのです。
たとえば、家が老朽化しており、壁や屋根が崩れそうな状態で周囲に危険を及ぼす場合は、行政が「特定空家」に指定することがあります。その後、所有者や管理責任者に対して解体や修繕を促す命令が出され、それに従わないと行政代執行となるケースも出てきます。
相続放棄をしていれば、このような措置に一切関係がなくなるというわけではないため、相続放棄と解体費用の関係は単純ではありません。また、建物構造によっては解体にかかる費用が大きく変動します。
木造の場合は比較的安価ですが、鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)になると費用は一気に高額になることも多いです。
家を解体する際の一般的な費用相場
空き家の解体費用は、家の構造や延床面積、周辺環境などによって大きく変わります。以下に、一般的な解体費用の相場についてかんたんにまとめてみました。
木造
1坪あたり3万円~5万円
鉄骨造
1坪あたり4万円~6万円
RC造
1坪あたり6万円~8万円
上記の金額はあくまでも目安ですが、同じ木造でも建物が密集地にある場合や、アスベストの除去が必要な場合は費用が上乗せされることがあります。
さらに、敷地の形状が複雑で重機が入りにくい場合や、廃棄物の運搬距離が長い場合にも追加のコストが発生する可能性が高いです。例えば、道路幅が極端に狭い場所にある家だと、重機が入れずに手作業で解体せざるを得ないケースも考えられます。
その場合、作業員の人数や作業時間が増えるため、結果的に解体費用が膨らむのです。解体費用を正確に知るには、解体業者や不動産会社に現地調査を依頼するのが最も確実な方法となります。
また、急いで解体せずに「一括見積サービス」などを活用して複数社から見積もりを取れば、ある程度の費用比較も可能です。
解体費用が高額になりやすい理由
解体費用が思った以上に高額になる理由は、家の構造や立地条件だけではありません。以下のポイントも大きく関係しています。
- 建物の特殊素材(アスベストなど)が使われている
- 行政指導による追加の撤去作業が必要になる
- 遺品整理や残置物処分に伴う費用が発生する
たとえば、古い家にはアスベストを含む建材が使われていることがあり、解体時には特殊な手順で撤去しなければいけません。
これにより専門業者による費用が通常より大幅にかかり、結果的に全体の解体費が高くなるわけです。また、行政指導によって「特定空家」指定を受けた建物は、周辺の安全を確保するために普通の解体よりも注意深い作業が必要になるケースもあります。
さらに、家の中に大量の残置物が残っている場合は、遺品整理業者や不用品回収業者などを別途手配しなければならず、追加費用が発生しやすいのです。こうした費用を想定せずに「これぐらいで済むはず」と楽観的に考えていると、想定を大きく超える出費に驚くこともあるかもしれません。
解体前には、専門家の意見を聞きながら、家の構造や内部の状態などをしっかりと確認し、どの程度の費用がかかるのかを正確に見積もることが非常に大切です。
相続放棄した家の管理責任と費用負担
「相続放棄をすれば、家を処分してしまえばいい」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、実際には相続放棄をしても、一定の条件下で管理責任や費用負担が残るケースがあります。
特に、2023年4月に施行された民法改正によって「保存義務」の対象がより明確化され、相続放棄したとしても放置は許されない状況が生まれることもあります。
これは、たとえ自分が相続したつもりがなくても、相続財産を占有していた場合に義務が生じる可能性があるというものです。例えば、被相続人と同居していた家に住み続けていたら、その家を管理する義務を負うとされる可能性が高いのです。
「相続していないのに何で私が管理しなきゃいけないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。しかし法律上は、相続放棄をしただけで完全に責任がなくなるとは限らず、放置して危険性が高まれば、近隣住民への損害や行政指導のリスクが避けられません。
民法改正で明確化された「保存義務」とは
2023年4月の民法改正では、相続放棄をした後の家の「保存義務」について大きくルールが変わりました。
ポイントは以下
- 相続放棄時に占有している人が、家の保存義務を負う
- 「保存義務を負う人」が管理を怠れば、行政指導などの対象になる
- 保存義務があるからといって費用負担が必ず生じるわけではないが、損害賠償リスクは否定できない
この「占有」とは、実際に家に住んでいるだけでなく、鍵を管理していたり、荷物を置いていたりするような状況を示す場合もあります。
たとえば、相続が始まってすぐに「放棄する」と決めていても、一時的に家の中の荷物を管理していたりすれば、民法改正後の解釈によって「占有者」とみなされる可能性があるのです。
専門家の言葉では、「相続財産清算人」や「特別代理人」の問題も絡んできて、誰がどこまで責任を持つのか非常に複雑になりがちです。保存義務がある場合、空き家をそのまま放置して家が倒壊する危険性が高まれば、行政から指導を受けることもあります。
こうした指導を無視し続けると、行政代執行による解体が行われ、その費用を請求されるリスクがあるため、相続放棄だけで終わらない点に注意してください。
相続放棄時に占有している場合の注意点
相続放棄を行った段階で、既に被相続人の家に居住していたり、物品を管理していたりする場合は要注意です。
- 放棄後も家の安全維持に協力しなければならないケースがある
- 放置して被害が出た場合、損害賠償を求められる可能性がある
- 行政代執行で解体されても費用負担のリスクが完全になくなるわけではない
具体的には、「家の玄関や窓の施錠をきちんと行う」「雨漏りで構造が危険な状態なら応急処置をする」といった最低限の管理は、相続放棄をしていても占有状態にあるなら求められることがあります。
また、いくら相続放棄をしたからといって、自然災害などで家が倒壊し、隣家に被害を与えた場合、賠償責任を負うことはゼロではありません。たとえば、もともと雨漏りが酷いのに放置して屋根が腐食し、大型台風が来たときに瓦が飛散して近所の車を破損させた場合など、過失を問われることがあり得るのです。
相続放棄後の家を放置した場合のリスク
相続放棄をすると、「もう自分のものではないから放っておいても大丈夫」と思い込みがちです。
しかし、空き家を放置しておくことには大きなリスクが伴います。
特に、家が老朽化して倒壊の危険がある場合や、近隣住民に被害をもたらす可能性がある場合には注意が必要です。行政は、地域の安全を守るために「特定空家」に指定して改善や撤去を促す命令を出し、最終的には行政代執行を行うことがあります。
こうなると、費用負担をめぐってトラブルが起きるだけでなく、近隣との関係が悪化する原因にもなりかねません。相続放棄をしているのにも関わらず、家が危険状態のまま放置されていると、行政や周囲から責任を追及されるケースが報告されています。
そもそも相続放棄をすればすべての負担から解放される、とはならないのが現実です。物理的に家を取り壊すか、あるいは売却などの手段を取らなければ、危険がある空き家は周囲に迷惑をかけるだけでなく、自分自身も法的トラブルに巻き込まれる可能性があるため、早期の対応が不可欠です。
倒壊リスクと行政代執行による費用
古い家を放置したままにしておくと、屋根や壁が崩れたり、地震や台風などの自然災害で一気に倒壊するリスクが高まります。
倒壊した場合、最悪の場合は周辺の建物や道路をふさいでしまい、大規模な被害を引き起こすことも考えられます。そうなれば行政や警察の対応だけでなく、損害賠償を請求される恐れも出てくるのです。
これを防ぐために、市区町村などの自治体は「特定空家等」に指定して所有者や管理者に警告を出し、それでも改善が見られない場合は行政代執行という形で強制的に解体を行います。行政代執行となると、費用は自治体が立て替えますが、その後に解体費用を請求されるケースがあります。たとえば、延床面積が大きい木造住宅や二階建て以上の建物だと、解体費は数百万円に及ぶことも珍しくありません。
相続放棄をしているからといって、行政代執行の請求が完全に免除されるわけではなく、状況によっては支払い責任を問われることもあるため要注意です。結果として、「相続したくないから放棄したのに、莫大な解体費用の請求が来た」となることを避けるためにも、家を放置するリスクを十分に理解しておく必要があります。
近隣被害が発生した場合の損害賠償責任
老朽化した空き家が原因で近隣住民に被害を与えた場合、相続放棄をしていても損害賠償責任を負うリスクは残ります。
- 強風で屋根の一部が飛ばされ、隣家の屋根や車を破損させた
- 土台が腐食して倒壊し、隣の家の塀を壊したり、道路を塞いで通行人にケガをさせた
- 害虫や衛生面の問題が深刻化し、周辺住民の健康被害を誘発した
例えば、台風のときに外壁が剥がれ、隣家の庭に落ちて物を壊してしまったというケースでは、管理が不十分だった点を指摘されて賠償請求を受ける可能性があります。
相続放棄をしているという事実だけで「無関係です」と突っぱねるのは難しく、特に相続放棄後も家に荷物を置いたり、実質的に占有していたとみなされれば責任追及されることがあるのです。
こういったトラブルは感情的にも大変ですし、金銭面でも大きな負担となるため、相続放棄をして家にかかわりたくないと考えるならば、早めに家を処分するか、管理をどうするか明確にする必要があります。
相続放棄しても解体費用を支払うケースはある?
「相続放棄をすれば家の解体費用は一切払わなくていいんですよね?」と聞かれることがありますが、必ずしもそうとは言い切れません。
たしかに、相続放棄をすれば法的には財産も負債も引き継がないというのが原則ですが、前述した「保存義務」が適用される場合は、自分が占有していた家を放置して危険を招けば、結果的に費用を負担するよう求められるケースもあるのです。
たとえば、行政代執行で強制的に解体されるまで何も対処しなかった場合、その解体費用を請求される可能性は残っています。また、相続人全員が相続放棄をしてしまうと、「相続財産管理人」が選任されることがあり、そこでも管理費用や処分費用などが問題となることがあります。
相続放棄は万能な解決策ではなく、状況次第で思わぬ費用負担が残ることを知っておく必要があります。
結局のところ、家そのものが存在する以上、誰かが管理をしなければならないため、放棄によって全員が逃れてしまうというわけにはいかないのです。
保存義務があるケース
相続放棄の後でも保存義務が残るケースは、前述のように「家を占有している」場合に特に問題となります。
- 相続人として名乗り出ていなくても、実質的に家を管理しているとみなされる
- 保存義務があると判断されれば、家が倒壊しないよう最低限の管理が求められる
- 費用を発生させないためにも、早めに引き渡しや解体、あるいは売却などを検討すべき
例えば、被相続人と一緒に住んでいた親族が「相続放棄をする」と決めたとしても、その家で日常生活を継続している場合は、民法改正によって占有者として扱われる可能性が高いです。
その結果、「保存義務」を怠ったとされれば、家が危険な状態を放置していたことに対して責任が問われるリスクがあります。相続放棄を選ぶにしても、完全に家から引き上げるか、速やかに相続財産管理人を選任して家の処分を進めるなどの対応が必要です。
行政代執行が行われた場合の対応
行政代執行が行われる場合、基本的には「危険な空き家だ」と判断された家を行政が強制的に解体する手続きとなります。
- 行政が解体費を立て替えた後、所有者や管理責任者へ費用を請求する
- 相続放棄によって所有権が不明確でも、占有者などが費用を負担するケースがある
- 特定空家などに指定された場合、優遇措置だった固定資産税の軽減もなくなる
例えば、自宅から離れた場所にある家を「相続放棄しているから関係ない」と思い放置していたところ、市区町村から何度も勧告や指導が入り、最終的に行政代執行で解体されてしまったという事例があります。
その際、膨大な解体費用が請求され、相続放棄をしていたにもかかわらず、結果的に負担を求められたケースもあるのです。行政代執行はそれほど頻繁に行われるわけではありませんが、ひとたび行われるとコストが高くつくことが多いため、事前の対応が非常に大切です。
相続放棄した家の解体費用が支払えないとき
「相続放棄をしたはずなのに、思わぬ解体費用が請求された」「そもそも高額すぎて支払えない」と頭を抱える方もいるかもしれません。
ここでは、そうしたケースに直面したときにどのような対策があるのか、具体的に考えてみましょう。
相続財産清算人の選任
相続放棄をした後に、誰も家を引き継ぐ人がいなくなった状態では、その家は「相続財産管理人」や「相続財産清算人」が管理する必要が生じることがあります。これらの存在は、専門家である弁護士や司法書士が担うケースが多いです。以下のポイントを覚えておきましょう。
- 裁判所への申立で清算人を選任できる
- 清算人は家や土地を売却したり、借金を返済したり、解体するなどの措置を行う
- 清算にかかる費用は原則として相続財産から支払うが、不足する場合は申立人が予納金を求められる場合もある
たとえば、家の価値よりも解体費用のほうが高くつくような状態だと、清算人を選任しても実際には「処分しても赤字」という事態になり、費用をどう工面するかが問題になります。
裁判所に申立てる際に予納金として50万円~100万円程度必要とされるケースも珍しくなく、「相続放棄で負担を減らすはずが、かえって大きな出費に」と嘆く方もいます。
しかし、清算人を選任しておけば、少なくとも個人が直接解体費用を請求されるリスクは減り、手続きの面倒さも大幅に軽減できます。
費用負担の目安と注意点
費用負担の目安としては、「解体費用」「清算人報酬」「行政代執行費用」など、いくつか考えられます。そこで、かんたんにまとめてみましょう。
解体費用
木造か鉄骨造かなどによって数十万円~数百万円と幅が広い
清算人の報酬
相続財産の規模やケースによって異なるが、目安は50万円以上の予納金が必要な場合あり
行政代執行費用
建物の状況や延床面積によって大きく変動し、個人解体より高額になる傾向がある
たとえば、築数十年の木造2階建てを解体するだけでも300万円前後かかることがありますし、RC造の大きな建物ならさらに高額になることが珍しくありません。
清算人報酬は相続財産から出すのが原則ですが、もし資産価値がほぼゼロの物件ばかりなら、申立人が事前に裁判所へ予納金を納めなければならない可能性があります。
また、行政代執行で解体された場合には、自治体が立て替えた費用が請求されるため、事前の工事見積もりよりも割高になりやすい点に留意してください。こうした費用負担を最小限に抑えたいと考える方は、早めに売却や適切な管理手段を講じることが重要です。
相続放棄だけで安心しきると、後々になって思わぬ負担を背負う可能性があるため、あらかじめ注意しておきましょう。
相続放棄以外の対処法:空き家売却という選択
相続放棄を検討する大きな理由として「家の維持コストや解体費用が重荷になりそう」という不安があるかと思います。
しかし、あえて相続放棄をせずに家を相続したうえで「空き家を売却する」という選択肢もあります。売却することで得られる利益があれば、解体費用をカバーできる可能性もありますし、場合によっては家をリフォームして賃貸に回すという手段も考えられるでしょう。
また、不動産会社によっては、建物を解体しなくても「現状のまま買取」してくれるところがあります。たとえば、一般的には老朽化が激しい空き家は「更地にしてから売却するほうが有利」と言われますが、必ずしもそうではありません。建物の立地条件や希少性によっては、古屋付きでも売却希望者が見つかるケースがあるのです。
売却にかかる税金とメリット
家を相続して売却する場合には、さまざまな税金が関わってきます。
- 印紙税:売買契約書を作成するときに必要
- 譲渡所得税:売却益(譲渡所得)が発生した場合に課税
- 住民税:譲渡所得税とあわせて課税される場合がある
たとえば、譲渡所得税は「売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた利益」に対してかかるため、家が古くてほとんど利益が出ない場合は、それほど大きな税負担にはならないこともあります。
一方、築年数は古いものの土地の価値が高い場所であれば、売却価格が想像以上に上回り、結果として余裕をもって解体費用や管理費用を賄えるケースもあるのです。
さらに、売却のメリットとしては「空き家による維持費や管理の手間から解放される」点が挙げられます。もしリフォームや解体にかかる費用よりも、売却益のほうが大きいと判断できれば、相続放棄をするより売却を選択するほうが利益につながる可能性が高いといえるでしょう。
解体せずに現状のまま売る方法
空き家を売却する際、「古い家だから解体して更地にしてから売ったほうがいいのでは」と思う方も多いでしょう。
たとえば、古民家としての趣がある木造住宅や、リノベーションの潜在価値が見込める物件などは、そのまま売ったほうが買主にとって魅力的な場合があります。
また、解体するとなると先述のとおり数十万円から数百万円のコストがかかるうえ、解体工事の日程調整や近隣への挨拶などの手間も必要です。そうした面倒を回避したい売主にとっては、現状のまま買い取ってくれる不動産会社がありがたい存在といえます。
最近は、不動産会社によっては「建物の構造や築年数は古くても、土地の立地に価値があれば買取可能」というスタンスをとっているところもあるので、一度査定を依頼してみるとよいでしょう。これにより、相続放棄せずに済み、トータルで見たときに利益を得られるかもしれません。
まとめ
相続放棄と空き家の解体費用の問題は、一見すると「相続放棄すれば解決」と思われがちですが、実は管理責任や保存義務といった複雑な要素が多く、単純には割り切れません。
放棄後も家を放置していると、行政代執行の対象になって解体費を請求されたり、近隣住民に損害を与えた場合に賠償を求められたりするリスクがあるのです。一方で、相続して売却する道もあるため、解体費や維持費と比較してメリットが大きいなら、そちらを選ぶのが得策かもしれません。
もし相続放棄を選ぶなら、相続財産清算人を立てて法的に整理する手段もあるので、早めに専門家に相談することが大切です。中学生でも理解できるように書きましたが、専門用語が入り交じる領域でもありますので、不明点があれば迷わず専門家に問い合わせましょう。