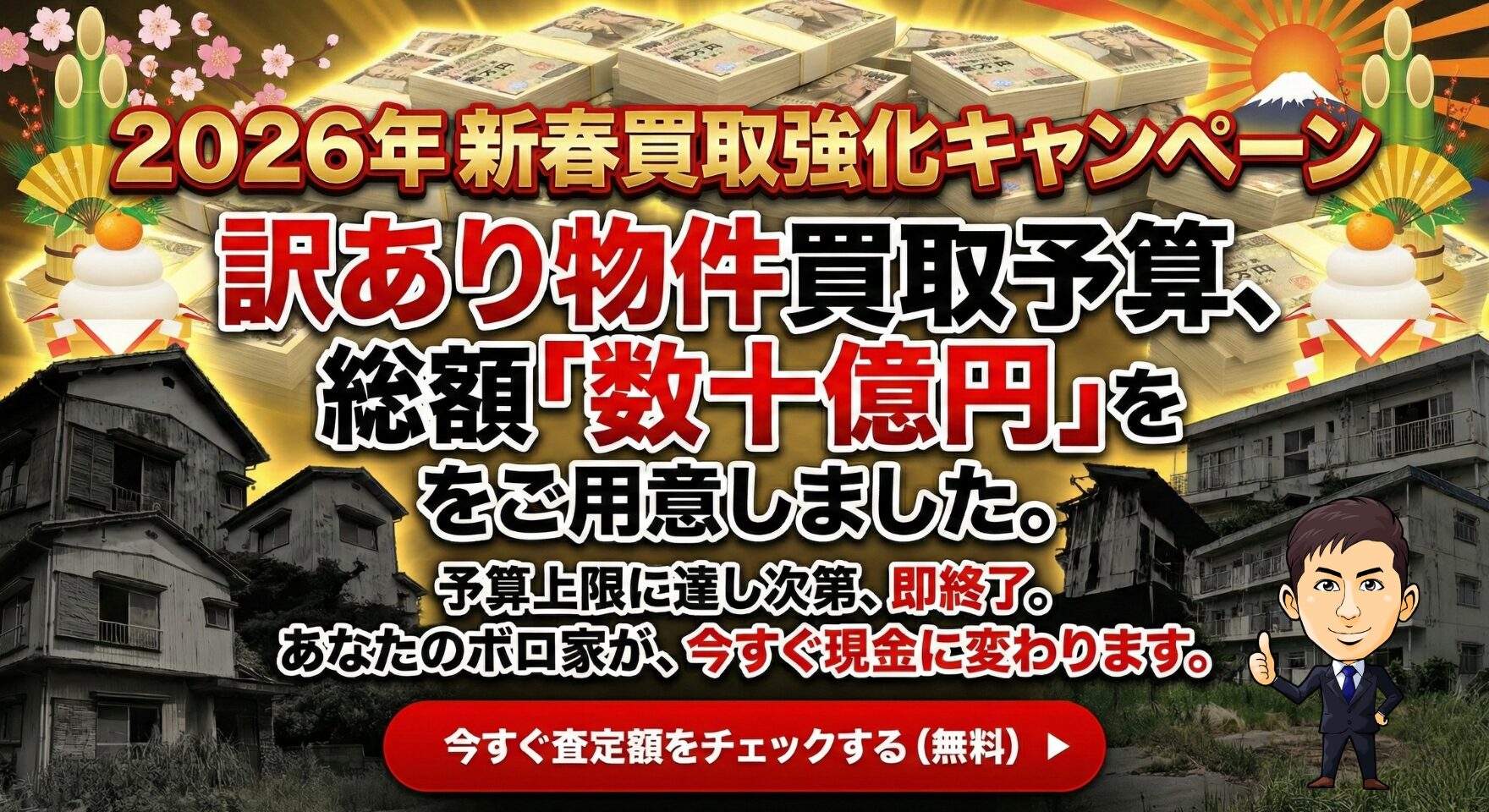持ち家・借地の相続は難しい?相続税や地主の承諾が必要なケースを解説

「家は自分のものだけど、土地は借りている」という不動産を相続することになったら、普通の相続とは少し違った対応が必要です。
結論からいうと、持ち家が借地に建っている場合の相続では、地主との関係や借地権の取り扱いに注意しないと、トラブルになりやすいです。
なぜなら、土地を借りている状態(=借地)では、相続後に地主の承諾が必要になったり、地代の値上げを求められたりするケースがあるからです。
特に「相続人ではない人に遺贈する場合」や「建物を売却する場合」などは、地主の許可が必要になりやすく、承諾料が発生することもあります。
たとえば、お父さんが亡くなって、子どもが家を相続する場合は地主の許可はいりませんが、その家を売ろうとすると地主の承諾が必要になります。このとき、「名義変更料」として借地権価格の5〜10%を求められることもあります。
つまり、「家は自分のものでも、土地が他人のもの」という状況は、思っているよりも手続きや交渉が複雑なのです。
記事では、これらのポイントをわかりやすく整理し、安心して相続を進めるための手順を解説していきます。
「持ち家が借地に建っている」相続の特徴とは?

持ち家が借地に建っていると、一般的な相続とは少し違った難しさがあります。
普通、家と土地はセットで自分のものですが、借地の場合は家だけが自分のもので土地は他人のもの。相続のときには地主さんとの関係がとても大切になってきます。
地主さんにきちんと連絡をしたり、時には承諾をもらう必要があったりと、借地ならではの特別な手続きがあります。また、土地の権利関係が複雑になるので、相続税を計算するときも特別な方法が必要です。
そもそも借地権とは何?
借地権とは、他人の土地を借りてその上に自分の建物を建てることができる権利のことです。
家は自分のものでも、土地は他人のものというちょっと不思議な状況ですね。
この借地権には「地上権」と「賃借権」の二種類があります。また、法律によって「旧法借地権」と「新法借地権」という区分けもあります。
「地上権」と「賃借権」って何が違うの?
借地権には「地上権」と「賃借権」の2つがあり、それぞれ性質が違います。
中学生でもわかるように簡単にいうと、地上権は強い権利、賃借権は少し弱い権利です。
具体的には次のような違いがあります。
- 地上権…地主さんにいちいち許可をもらわなくても土地を自由に使え、売ったり貸したりも自由にできます。でも、登記という正式な手続きが必要です。
- 賃借権…地主さんの許可を得て土地を借りる権利で、勝手に土地を人に貸したり売ったりできません。でも、登記をしなくても建物があれば権利を主張できます。
例えば、地上権は自分のものを自由に使う「持ち家」に似ていて、賃借権は大家さんに家賃を払って借りる「賃貸アパート」に似ていますね。
旧法借地権と新法借地権はここが違う!
借地権には昔の法律に基づいた「旧法借地権」と、現在の法律で定められた「新法借地権」があります。
旧法借地権は昔から続いているもので、借りる側に有利にできています。
一方、新法借地権は地主さんにも優しく、契約期間がはっきり決まっています。
- 旧法借地権…契約期間が終わっても借り続けることが比較的簡単です。昔ながらの借地でよくあるタイプ。
- 新法借地権…定期借地権ともいい、契約期間が終わったら必ず土地を返すことが決まっています。地主さんにとって将来の計画が立てやすくなっています。
例えば、祖父母の時代から続いている家の土地は旧法借地権で、新しくマンションが建つ土地は新法借地権が使われることが多いです。
借地権付き住宅のメリット・デメリット
借地権付き住宅には良いところと注意点の両方があります。
自分の家を持ちたいけれど土地代が高くて大変という人にはピッタリな方法ですが、注意することもあります。
- メリット
・土地代が安いので、家を建てやすい
・税金(固定資産税など)が地主負担なので節約できる
・良い立地に住めることが多い - デメリット
・毎月地主さんに地代を払う必要がある
・家を売ったり、リフォームするときは地主の許可がいる場合がある
・土地が自分のものにならないので将来が不安
東京の駅近の土地に自分の家を建てたいけれど、買うお金がないときには借地権付き住宅が現実的です。ただし、土地がずっと自分のものにならないことは忘れないでください。
地主とのトラブル!よくある問題と解決法を解説
土地は地主さんのもので、自分の家だけが持ち家という場合、相続をきっかけにトラブルが起こることも珍しくありません。ここでは、そんな地主さんとの間で起こりやすい問題とその具体的な解決法をわかりやすくお伝えします。
なぜ地主さんの承諾が必要?遺贈や第三者譲渡で注意すべきポイント
自分の土地でない借地に建っている家を「遺贈」や「第三者譲渡」するときには、地主さんの許可(承諾)が必要になります。
遺贈とは、遺言で相続人以外に財産を譲ることです。
例えば、「長年お世話になった近所の人に家を残したい」と考えて遺言を書いた場合には、地主さんの承諾を取らないと、その遺贈が無効になったりトラブルになったりすることがあります。
また、第三者に家を売却する場合にも、同じように地主さんの承諾が必要です。
承諾が必要な理由は
- – 借地契約は地主さんと借地権者(あなたや相続人)との間の契約であり、地主さんにとっても誰が住むか重要だからです。
- – 勝手に第三者に譲渡すると、地主さんの権利が不安定になる恐れがあるためです。
- – 承諾を得ないまま譲渡した場合、地主さんから契約を解除される可能性があるからです。
地主さんが承諾しない場合、家庭裁判所に「借地非訟手続き」という申し立てをすることもできます。法律の専門家(司法書士や弁護士)に相談すると安心です。
地主さんの承諾はトラブル回避の大切なポイントです。必ず事前に地主さんとコミュニケーションを取るようにしましょう。
地主さんに払う「譲渡承諾料・名義書換料」の相場
地主さんの承諾を得て借地権を第三者に売却したり、名義を書き換えるときに必要になるのが「譲渡承諾料」または「名義書換料」です。
これは地主さんに対して、「名義変更を認めてくれてありがとう」という気持ちで払うお金のようなものですが、金額の相場を知っておくと安心して交渉できます。
- – 一般的に借地権価格の5%~10%程度
- – 借地権の価値が1,000万円の場合、承諾料は50万円〜100万円程度が目安
地域や地主さんによって多少の差があります
例えば、東京の下町など地価が高い地域では、地主さんから相場より高めの承諾料を求められることもあります。
こうした場合は、土地の価格を専門家に相談し、交渉の余地があるかを検討しましょう。また、地主さんとの関係が良好だと、承諾料を安くしてもらえることもあります。
もし交渉が難しければ、不動産会社や司法書士、弁護士など専門家に間に入ってもらうことも検討してください。
地主さんから「地代の値上げ」を求められたらどうする?
相続が起きると、地主さんから「今までの地代を値上げしてほしい」と言われることがあります
地代値上げを求められたときの対応方法が
- – なぜ値上げが必要か理由を地主さんに聞く(例:固定資産税が高くなった、近所の地代が上がったなど)。
- – 理由に納得できる場合は、妥当な範囲で値上げに応じる。
- – 納得できない場合や、あまりにも高額な値上げの場合は、法律の専門家(司法書士や弁護士)に相談する。
- – 地主さんが地代の受け取りを拒否した場合は、「供託」という制度を利用し、法務局に地代を預けてトラブルを避ける。
例えば、「地代が急に2倍に値上げ」と言われても、その根拠が明確でない場合、交渉することが可能です。
専門家を交えて妥当な金額を提案することで、話し合いがスムーズになります。
「立ち退き要求」を受けた時に覚えておきたい注意点と対応策
地主さんから「土地を返してほしい」と立ち退きを要求もゼロではありません!
立ち退きには「正当な理由」(正当事由)が必要で、地主さんの一方的な都合だけでは認められないケースも多いのです。
ずばり、地主さんが「土地を売りたいから出ていって」と言っても、借地契約がある限り簡単には立ち退かせることはできません。
まとめ:「借地に建つ持ち家」を相続するなら準備がカギ!
借地に建つ持ち家の相続には、特別な知識と準備が必要です。土地が自分のものでないことから、地主さんとの関係を良好に保つことがとても重要になります。
相続が始まってから慌てることがないように、事前に専門家に相談したり、必要な手続きや承諾料、税金についてもきちんと調べておきましょう。
「難しそう」と思うかもしれませんが、事前にしっかり準備をしておけば大丈夫です。