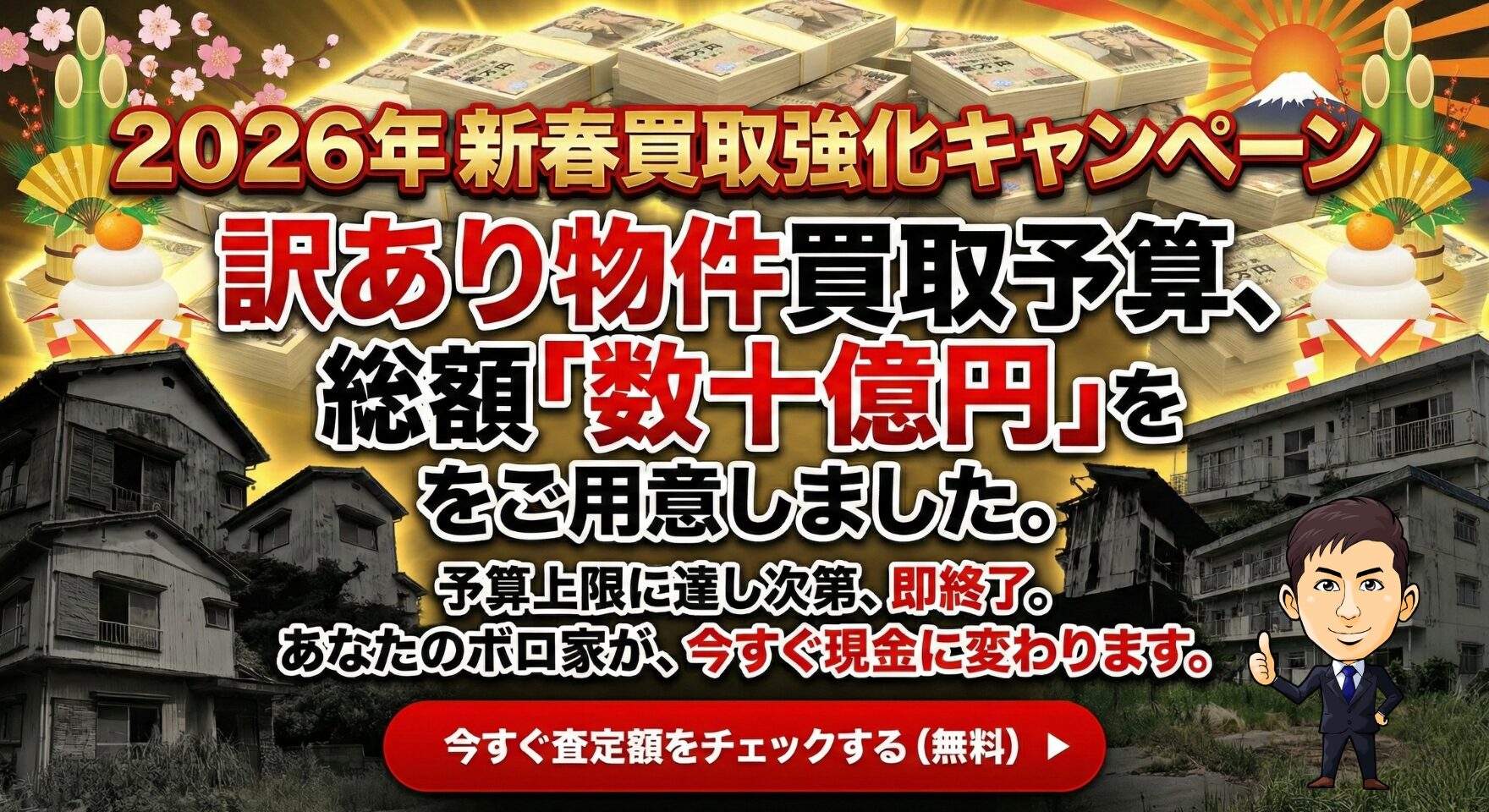成年後見制度で認知症でも自宅を売却できる!
認知症の親の自宅を売却したいけれど、どう進めればいいのか迷っていませんか。結論から言うと、成年後見制度を利用すれば、認知症でも自宅を合法的に売却できます。
なぜなら、意思能力が低下した本人に代わり、後見人が家庭裁判所の許可を得て売買契約を結べるためです。
たとえば、過去のお客様である判断力が衰えたAさんのケースでも、子どもが後見人となり許可を取得し、売却代金を介護費に充てられた実例があります。
つまり、正しい手順と準備を知れば、家族の生活資金を確保しながら安心して手続きを進められるのです。
認知症でも自宅売却はできる

親が認知症と診断されると、家族は介護や資金面で大きな不安を抱えます。
特に住み慣れた自宅を手放すかどうかは心の痛む選択ですが、結論から言えば、法律のルールを守れば認知症になっても自宅を売却することは可能です。ポイントは「本人の意思能力」と、それを補う制度である「成年後見制度」の活用にあります。
売却可否のカギは「意思能力」
自宅を売れるかどうかを左右する最大のポイントは、所有者に『意思能力』が残っているかどうかです。
この意思能力とは、契約内容を理解し、自分の判断で売買の承諾ができる力を指します。
程度に応じて「完全にある」「部分的にある」「ほとんどない」と分かれ、区別を誤ると契約無効や詐欺被害に発展するおそれがあります。
家族が日常会話で確認できるサインから、臨床心理士や精神科医が行うMMSE(認知機能検査)の数値まで、判断材料を具体的に示します。
さらに、意思能力の有無をめぐって家族間で意見が割れたときに役立つ『鑑定意見書』や『公証人の面前確認』といった専門手続きもあります。
意思能力とは何?
意思能力とは、民法で明文化されないものの判例で確立された概念で、売買契約の意思表示が有効かどうかを測る土台になります。
簡単に言えば「この契約を結ぶと自宅が他人の名義になり、自分に代金が入る」という因果関係を理解し、自らの価値判断で賛成・反対を選べる心の力です。
精神疾患の診断基準DSM‑5でも「判断力の保全」は重要な評価項目とされ、後見開始の審判では精神科医の鑑定書が引用されることもしばしばあります。
- ・契約内容を理解しメリット・デメリットを比較できる状態
- ・売却後に所有権が移転する結果を認識している状態
- ・他人からの不当な影響なく自分の意志で決定している状態。
これら三つがそろえば、たとえ軽度認知症でも法律上は売却が可能と評価される余地があります。
逆にいずれかが欠けると、意思能力なしと判断され、契約は取り消し対象になります。
医師の診断書で証明する手順
医師の診断書は、家庭裁判所が意思能力の有無を判断する一級資料です。
手順はまず、物忘れ外来や精神科で「成年後見用診断書」フォームを依頼し、MMSEや長谷川式スコア、CT画像所見などを盛り込んでもらいます。
次に、ご家族立会いの下で医師が契約内容を説明し、本人がどこまで理解できるかを問診します。その様子はカルテに残り、場合によってはビデオ撮影を添付することもあります。
最後に、医師は『意思能力は保持』『限定的保持』『欠如』のいずれかを明記し、裁判所提出用として封印します。
トラブルを避けるための証拠保全ポイント
意思能力の有無をめぐる争いは、売却完了後にきょうだい間や買主との間で起こりやすいものです。
将来の「言った・言わない」を防ぐために、取引プロセスを証拠として残すことが欠かせません。
例えば、公証人役場で『意思確認公正証書』を作成すれば、公証人が面前で質問し記録してくれるため、第三者性が担保されます。
また、不動産会社との媒介契約書や重要事項説明書に署名する場面を動画に収め、クラウドに保存する方法も有効です。
これらの資料は、裁判所や金融機関から提出を求められた際に力強い後ろ盾になります。
成年後見制度の基礎知識
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人を法律面・生活面で支える仕組みで、2000年に導入されました。
大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二系統があり、前者はすでに意思能力が低下した段階で家族や市町村長が裁判所に申し立て、裁判所が後見人を選任します。
後者は、まだ本人がしっかりした意思を持っているうちに、将来を託す信頼できる人と公正証書契約を結び、判断力が低下したときに発動する予防的制度です。
ここでは、両制度の発動要件、権限範囲、コスト面を比較し、どちらを選ぶと自宅売却がスムーズかを具体例で解説します。
専門家しか使わない『専任鑑定』『身上監護』といった用語もかみくだき、家族が自力で制度設計できるようサポートします。
成年後見制度が必要になるケース
認知症でも日常生活に大きな支障がなければ、成年後見を使わずに済む場合もあります。
ところが自宅売却のように〈高額・不可逆〉の取引を行うときは、裁判所の関与が必須とされ、後見制度の利用がほぼマストになります。具体的には、本人が登記識別情報(旧権利証)の意味を理解できない、金銭感覚が薄れて詐欺被害に遭いやすい、固定資産税や公共料金の支払い管理が困難、といった場面が該当します。
- ・高額取引で契約内容を理解できないとき
- ・売却代金の管理ができず詐欺リスクが高いとき
- ・公共料金や税金の滞納が始まったとき
制度を利用することで、後見人が代わりに契約を締結し、金融機関への着金確認から納税手続きまで一気通貫で管理してくれるため、家族の精神的・時間的負担も大きく軽減されます。
法定後見の3区分
法定後見は、本人の判断力の程度によって『後見』『保佐』『補助』の三段階に分かれます。
後見はほぼ意思能力がない状態で、後見人が広範囲の代理権を持ちます。保佐は意思能力が著しく不十分で、重要な財産行為には保佐人の同意が必要です。補助は比較的軽度で、本人が代理権や同意権を限定的に付与できます。
どの区分でも自宅の売却は「居住用不動産処分」に当たり、家庭裁判所の許可が前提となる点は共通です。
- ・後見=意思能力なし、代理権フルセット
- ・保佐=同意権中心、一定の代理権付与可能
- ・補助=必要な範囲のみ代理・同意権設定。
区分選定は医師の鑑定と裁判所の調査官面談に基づき決まるため、診断書の記載内容が分岐点になります。
自宅売却を予定しているなら、早期に医師へ目的を伝え、具体的な生活場面での判断力を詳細に記録してもらいましょう。
任意後見契約の仕組みとメリット
任意後見契約は、まだ元気なうちに将来の財産管理を信頼できる人へ託す“保険”のような制度です。
公証役場で公正証書を作成し、登記まで済ませておくと、本人の判断力が低下したタイミングで後見がスタートします。
自宅売却を視野に入れた契約内容なら、売却時期や価格下限、資金の使途をあらかじめ条項に盛り込めるため、実務で迷う場面が激減します。
また、後見人候補を家族ではなく信託銀行や司法書士法人に指定すれば、親族間トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
任意後見は発動後も家庭裁判所の監督が付き、監督人が後見人の業務をチェックするため、売却価格が不当に安くなるリスクも低減される点が大きなメリットです。
後見人の権限・義務・報酬の相場
成年後見人は、本人の財産と身上(生活)を守る“代理人”かつ“監督対象”という二重の立場に立ちます。
権限は代理権・同意権・取消権で、代理権には売買契約締結、同意権には銀行解約手続き、取消権には本人が誤って結んだ契約の無効主張などが含まれます。一方で、財産目録の作成や年次報告書の提出義務が課され、怠れば報酬減額や解任の可能性もあります。
報酬は家庭裁判所が決定し、資産額と業務量に比例して月額2万円〜6万円が一般的です。
- ・代理権=契約締結や登記申請を代行
- ・同意権=本人の法律行為に事前承認を付与
- ・報酬は月2万〜6万円、資産規模で変動。
不動産売却のような大口処分を行う年には、別途『臨時報酬』が認められることも多く、その額は売却価格の1〜3%程度が目安とされています。
こうした費用をあらかじめ予算に組み込むと、後で驚くことがありません。
成年後見人を選任する手続きと必要書類
後見人を付けるには、まず家庭裁判所への申立てが必要です。申立書には本人や申立人の情報のほか、財産目録、親族関係図、診断書など多岐にわたる資料を添付します。
裁判所は書面審査と面談を経て、後見人候補の適格性や本人の希望を総合評価し、最終的に審判を下します。
選任されるまでの期間は平均2か月〜6か月ですが、書類不備や医師鑑定が入ると長期化します。
ここでは、申立てルートの全体像を丁寧に解説し、一つでも漏れがないようチェックリスト形式でポイントを提示します。専門用語の『身上監護』『保佐人付与審判』なども例示し、実務家と同じ視点で準備が進められるようナビゲートします。
さらに、申立手数料や郵券(裁判所に支払う切手代)、登記事項証明書の取得費用など、見落としがちな実費も具体的に提示しますので、予算組みの際に役立ててください。
申立てができる人とタイミング
申立てができるのは、民法上の4親等以内の親族、配偶者、本人自身、市区町村長などです。
家族が遠方に住んでいて手続きが難しいときは、福祉課に相談すると市区町村長申立てを代行してくれます。
タイミングは、銀行口座の凍結リスクや詐欺被害の兆候が出た段階が目安で、早すぎても遅すぎても手続きがこじれる傾向があります。
実務では、高齢者住宅への転居や施設入居の契約時期が迫った瞬間が申立てのハイシーズンです。理由は、入居一時金の支払いと自宅売却を同時に動かす必要があるためで、後見人の選任が遅れると資金計画が頓挫してしまいます。
診断書・財産目録など必須書類一覧
裁判所は「診断書」「財産目録」「収支予定表」「親族関係図」の4点セットを特に重視します。
診断書は前述のとおり判断能力の程度を示す心臓部の書類で、原本提出が必須です。財産目録は預貯金、不動産、株式、生命保険、負債を網羅し、最新残高証明や登記事項証明書を添付します。
収支予定表では、売却後の介護費用・家賃・医療費などの支出計画を具体的に示すと審査がスムーズです。
親族関係図はエクセルで作成しても問題ありませんが、住所・連絡先・高齢度を正確に記載しましょう。
家庭裁判所の審査フローと期間の目安
申立て後、裁判所は書面審査→調査官面談→医師鑑定(必要時)→審判書発送というステップで進みます。書面審査では不備がないかチェックされ、不足があれば補正命令が届きます。調査官面談は本人・申立人の双方に行われ、生活状況や資産状況を把握するヒアリングが実施されます。
医師鑑定は判断力が境界線上のケースで行われ、鑑定意見書が後見類型を左右します。
一般的な期間は2か月〜3か月、鑑定が入ると+2か月、書類補正が続くと半年を超えることもあります。
成年後見制度を使った自宅売却の具体的プロセス
後見制度を活用して自宅を売却する場合、通常の不動産取引よりも手順が多く、関わる専門家も増えます。
まず、後見人が売却の必要性を判断し、家庭裁判所に『居住用不動産処分許可申立書』を提出します。
許可取得後、不動産会社と媒介契約を締結し、査定書を添付して再び裁判所へ報告。買主が決まったら、売買契約書ドラフトを提出し、最終許可を得て決済へ進みます。
家庭裁判所の許可申請(居住用不動産処分許可)
処分許可申請は後見人業務の大一番です。
申請書には売却理由、予定価格、資金使途を詳細に記載し、査定書や建物状況調査報告書を添付します。
裁判所は「本人の居住環境」「売却価格の妥当性」「代替資金計画」を総合評価し、許可・不許可を判断します。許可が下りると、審判書が発行され、登記識別情報の代理受領や売買契約の締結が可能になります。
売却が介護費用や施設入居費に直結する場合は、パンフレットや見積書を添付すると説得力が増し、許可率アップにつながると多くの専門家が報告しています。
不動産会社選定から媒介契約を結ぶコツ
後見案件では、スピードと透明性が重視されるため、レインズ登録率が高く高齢者取引の実績が豊富な仲介会社を選ぶのが鉄則です。
媒介契約は「専任」か「専属専任」にすると活動報告が義務化され、後見監督人や裁判所への説明が簡単になります。
契約時には『成年後見案件であること』を明記し、売却価格の根拠として取引事例比較法・収益還元法の査定書を受け取りましょう。
なお、後見案件では値下げ交渉の根拠も裁判所に提示する必要があるため、初期設定価格は相場の上限ギリギリを狙うより、根拠が明確な適正価格に設定するほうが結果的に許可取得までの時間が短くなります。
売買契約・決済・登記の実務ポイント
売買契約書には、成年後見人が代理人として署名押印し、審判書の写しを添付します。
手付金受領時に発行する領収書も後見人名義で作成し、銀行には後見人の届出印を事前登録しておきます。決済当日は司法書士が同席し、登記原因証明情報に審判書を添付して代理権を証明します。
登記完了後は、法務局から登記識別情報通知書が後見人に交付され、報酬計算の基準となる資産売却報告書を裁判所へ提出します。
売却代金の管理と使途制限
売却代金は後見人名義の管理口座に入金し、使途のたびに領収書と振込控えを保管して年次報告書に添付します。
介護費用や施設入居費、医療費など本人の生活維持に必要な支出は許可されますが、相続税対策としての高額贈与や親族旅行の費用などは「本人利益」に当たらず、家庭裁判所が却下するケースが多々あります。
使途に迷う場合は、監督人に事前相談し『指示書』をもらうと安心です。
うっかり使途を誤ると、後見人個人が損害賠償責任を問われる可能性もあるため、支出の可否を「本人利益原則」に照らして慎重に判断しましょう。
意思能力が残っているうちにできる「家族信託」という選択肢
家族信託は、認知症リスクに備えて資産管理をオーダーメイドで設計できる柔軟なスキームです。
信託財産を自宅だけに限定し、受託者(子ども)が売却権限を持つ契約を公正証書で作成しておけば、後見制度よりも短時間で売却が実現します
しかも裁判所の許可が不要なため、タイミングを逃さず市場価格の高いうちに手放せるメリットがあります。
家族信託の仕組みと成年後見制度との違い
家族信託は、所有権を『名義=受託者』『利益=受益者』に分けることで、管理と享受を切り離す点が特徴です。
後見制度が“代理”による管理なのに対し、信託は“名義変更”による直接管理なので、売却のたびに裁判所許可を得る必要がありません。
その一方で、信託監督人や受益者代理人が置かれていないケースでは、不透明な運用が発生しやすいリスクがあるため、契約条項でチェック体制を強化することが重要です。
また、後見制度では売却代金が本人の財産として課税対象となりますが、信託の場合は受益者課税となり、場合によっては贈与税の猶予が受けられるなど税務上の差異も生じます。
信託契約を公正証書で作成する流れ
公正証書信託を作るには、まず信託士業者や司法書士と相談し、信託目的、受託者、受益者、残余財産帰属者を決めます。
次に、公証役場で契約条項案をもとに公証人と事前打合せを行い、手数料を確認します。
当日は本人・受託者・代理人が出席し、本人の意思確認後に署名押印し、信託登記を申請します。
作成費用は公証人手数料が数万円、司法書士報酬が10万円前後、登録免許税は固定資産評価額の0.4%が目安となりますが、後見制度の報酬が継続的に発生するのに対し、信託は初期費用で完結する点がコスト面の魅力です。
自宅売却後の資金管理を設計する方法
売却代金を信託口口座に入れると、受託者が受益者(親)の生活費や介護費に応じて給付できます。
毎月の定期給付方式や、医療費発生時のみスポット給付する方式など、条項を自由に設計できるのが強みです。
さらに、残余財産を相続時に孫へ教育資金として給付するよう設定すれば、贈与税の非課税枠内で世代間資産移転も可能です。
金融機関の中には信託口口座の通帳にWeb明細を付け、家族でリアルタイム閲覧できるサービスもあり、ガバナンスと利便性を同時に確保できます。受託者が複数いる場合は、支出額の上限を定めたり共同署名方式にすることで、不正利用への歯止めを一段と強化できます。
まとめ
認知症による自宅売却は、意思能力と制度選択が鍵。後見か信託かを見極め、裁判所許可や証拠保全を怠らなければ、家族は安全に資金を確保し、介護生活へ早期に備えられます。早めの情報収集が未来を守ります。